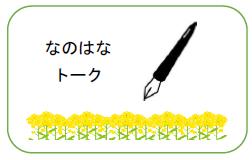|
262号2月28日 |
|||
|
|||
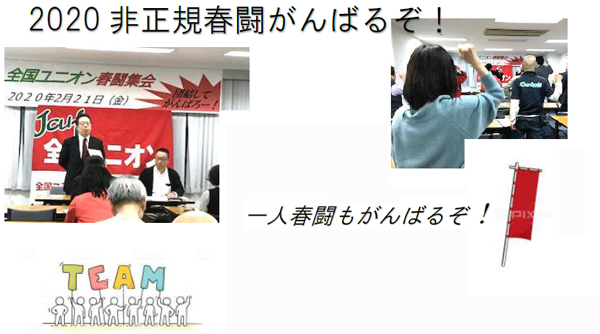 2月21日、全国ユニオン「2020春闘開始集会」が行われました。集会冒頭、鈴木会長が「全国ユニオンとして申し入れ行動に取り組み春闘を可視化しよう。スト権を確立するなど多様な戦術を駆使して春闘をたたかおう。底上げに取り組み、格差是正春闘にしよう。」と挨拶がありました。続いて各ユニオンから春闘の取り組みが報告されました。なのはなユニオンは、今年の4月1日に施行される「パートタイム・有期雇用労働法」を活用し正社員との格差是正を柱として春闘をたたかうということで、Mさん(ロイヤル)とSさん(オリエンタルランドユニオン)が報告しました。春闘開始が宣言されました。全国ユニオンは2月27日春闘申し入れアクションを取り組みます。一番はOLC本社(舞浜)です。 |
|
格差是正春闘2020、全力で取り組む!
オリエンタルランドユニオン
オリエンタルランドユニオンは、2020年4月1日に施行される「パートタイム・有期雇用労働法」<不合理な待遇差の禁止、待遇に関する説明義務の強化>を活用して、正社員との格差是正を柱に2020春闘に取組みます。
1.正社員と非正規社員の格差是正を求めます。具体的には以下のとおりです。

1.出演者の賃金について キャストに支給されている時間帯手当、着替え手当、高温度作業手当、ボーナスを同額支給に。
2.評価制度の撤廃を求めます。
3.無期転換者については、年に一度のオーディション制度を廃止する。
4.労働環境 (1)楽屋の環境整備、(2)着替え場所の整備、(3)悪天候時のキャンセル判断の変更を求めます。
(1)事前協議・同意約款(賃金、諸手当、労働条件等)の締結、(2)組合事務所、組合掲示板の設置、 (3)チェックオフ協定を締結、(4)組合員の特別扱いを行わない |

 方向性を確認するには至りませんでした。原告Bだけではなくて、現在、労災で休んでいる他の出演者からも、100%ありきでは復職できないので復職支援プログラムの柔軟化をという声があがっています。ユニオンは、この問題での交渉を継続します。
方向性を確認するには至りませんでした。原告Bだけではなくて、現在、労災で休んでいる他の出演者からも、100%ありきでは復職できないので復職支援プログラムの柔軟化をという声があがっています。ユニオンは、この問題での交渉を継続します。