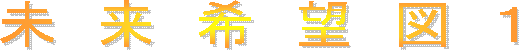
小学生最後の春休み、光熱斗の部屋には、彼にしては珍しい音楽が流れていた。ところどころ音が飛びながらも、どこか物悲しいメロディーの、スローテンポのジャズ。
熱斗は、繰り返しその曲を再生する。
「今日もこの曲なんだね、熱斗君」
「最近忙しくて、音楽なんか聞いてる暇なかったもんなー」
おどけた口調で熱斗は答えるが、それだけではないことを、ロックマンは知っている。
今、彼の部屋に流れている曲はバレルからの遺言により届けられたメディアチップの中身だった。といっても、この『バレル』は、熱斗の世界のバレル すなわち、デューオの紋章を持ち、デューオ、カーネルと共に宇宙に旅立った方のバレルだ。何故か、そのバレルの遺言が、彼の死後一年以上経ってから、届けられたのだ。父、祐一郎の説明では、本人からの期日指定と、軍の調査のせいだったらしい。確かに「こちら」のバレル大佐が亡くなった時、まだ熱斗はバレルの存在すら知らなかった。そんな相手から形見の品が送られたとしても、受け取りはしなかっただろう。
形見の中身は、バレルからの手書きの手紙と、一枚のレコード、そして一枚のメディアチップだった。
つい先日、一つの戦いが終わった。戦いの終わりは、常に別れを伴なっている。
今回の、グレイガ、ファルザー、そしてビヨンダート絡みの戦いもそうだった。ロックマンを兄のように慕っていたトリル、そしてビヨンダートのバレル、カーネル、そしてアイリス達 。
何度経験しても、別れは慣れない。
特にバレルとカーネルは、こちら側での別れの繰り返しだった。異世界の彼らだったとはいえ、外見も性格もほとんど二人に変わりはなかった。
だが、もう二人には会えない。
住む世界が違う。何よりカーネルは、電脳獣を封じるために、ビヨンダートを、熱斗達の世界を護るために、アイリスとともに消滅してしまったのだ。
そのメディアチップを、最近頻繁に熱斗は再生する。今まで聞かなかったのは、ビヨンダートのバレルと、「こちら」側のバレルに、何とか折り合いをつけるためだった。
最も、わざわざこの曲を熱斗に贈ってきたバレルの意図も、二人には分からなかった。わざわざ遺言執行の日時を死亡日からずらし、お気に入りらしいとはいえレコードをわざわざメディアチップに移してまで、贈ってきた意図が。
「いい曲だよね」
「うん。バレルさんらしい曲だよ」
「わざわざメディアチップにデータ変換してまでなんて、よっぽど熱斗君に聞かせたかったんだね」
そんな会話をポツリポツリと交わしながら、二人はメロディーに耳を傾ける。
何度目かの再生が始まった時。
「あれ?」
PETの中でメロディーを追っていたロックマンは、自分のすぐそばで点滅をしている信号に気付いた。
「どうした、ロックマン」
「メールが来たみたいだ」
回線を開くと、珍しいことにメールを運んできたのは、汎用ナビだった。
「ロックマン、お届け物です」
平坦な声で、汎用ナビがメールを差し出した。
「どうもありがとう。あ、僕宛だ」
受け取りつつ、ロックマンは差出人を確かめたが、差出人名はなかった。
「誰からだ、ロックマン」
画面の向こうから、熱斗が尋ねた。
「それが、名前がないんだ」
「えー…差出人わかんないのかよー。…大丈夫なのか、それ」
「うん…ウイルスチェックしてみるね」
メールをためすがえすしながら、ロックマンはとりあえず、ウイルスチェックを行う。
外見は、いまどき珍しい白封筒の簡素な形をしていた。素っ気無いといっていい程だ。
結果はすぐに出た。異常はない。しかも重さも、軽かった。添付ファイルなどは付いておらず、本文も文字データだけのようだった。
「熱斗君、どうしよう、これ」
「んー…とりあえず、開けてみたらどうだ?ダイレクトメールならそれまでだし、ウイルスも、変なファイルもくっついてなかったんだろ?」
「そうだね。とりあえず、開けてみるよ」
恐る恐る、ロックマンはメールを展開してみた。中身は、短い一文だけだった。
だが読んだ瞬間、ロックマンの顔色が変わった。
「熱斗君!!僕ちょっと出かけてくるよ」
そう叫ぶと、ロックマンは手紙を握り締めたままPETから走り出していた。
ロックマンは全力疾走でネットワーク内を突き進む。
途中ロールやガッツマンの声や姿が脇を掠めたが、ロックマンは気にも留めない。
今はそれよりも、メール内容の確認の方が先立った。
“ で待つ”
指定された場所は、よく知っている。
そこに行くための最短距離を計算し、いくつものショートカットを作成する。
電脳の世界と、現実世界の距離は違う。だが、現実世界に光ファイバーなどのネットワークが形成されていなければ、電脳世界の移動も無理なのだ。そしてその複雑さは、現実世界を凌駕する場合さえある。
出来るだけ早く、あの場所に。
今のロックマンの思考を占めているのは、それだけだった。
場所は、アメロッパにある、マンションの一室。
高速回線の中すら走り、ロックマンは先を急ぐ。通り過ぎる様々な情報が光の矢となって後方へ流れていく様は、流星のようにも見えたが、今のロックマンの目には入っていない。
ただ前に、前に。先に進むことが全てだった。
いるはずのない相手からの、届けられるはずのないメール メールには、時間や日にちを指定する類の言葉は一つもなかった。けれどロックマンは、じっとなどしていられなかったのだ。
マンション全体をつかさどる電脳空間の入り口で、やっとロックマンの足は止まった。後は、ここから個別の部屋に進むだけだ。
あの部屋に。一年以上も前に、住人が死去したはずの、あの部屋に。