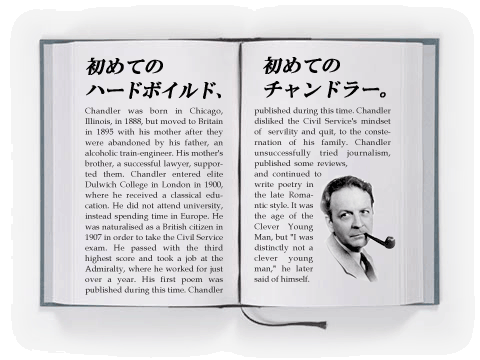
|
ようこそ「レイモンド・チャンドラーの世界」へ。
このページはこれからハードボイルド小説に挑戦しようと思っている方のために作りました。 多くは私の個人的な見解ですが、少しでも参考にしていただければ幸いです。 一緒にハードボイルド小説を楽しみましょう。 | |
| ハードボイルドって何だろう | |
ハードボイルド小説はいわゆる古典的ミステリーから派生した亜流の一つといえます。または、イギリスで生まれたミステリーがアメリカに適応した形と言ってもいいかも知れません。 | |
 ハードボイルドは古典的ミステリーから謎解きの要素を少々削り、その分、登場人物や事件の背景を描く事に力を入れ、リアリティーとドラマ性を追求しようとしているのが特徴です。結果、度肝を抜かれるようなトリックや思いもよらぬ真犯人が最後の最後に明らかになる、といった事のみに力点を置かない、誤解を恐れずに言えば「大人のミステリー」として結実しました。
ハードボイルドは古典的ミステリーから謎解きの要素を少々削り、その分、登場人物や事件の背景を描く事に力を入れ、リアリティーとドラマ性を追求しようとしているのが特徴です。結果、度肝を抜かれるようなトリックや思いもよらぬ真犯人が最後の最後に明らかになる、といった事のみに力点を置かない、誤解を恐れずに言えば「大人のミステリー」として結実しました。
多くの場合、主人公は職業探偵で、依頼人からの報酬を得るために事件と向き合います。天才的な頭脳や閃きに頼らず、自らの足を使って捜査にあたり、その過程で危険な目に遭ったり、別の事件に巻き込まれたりすることもしばしば。それでも、彼らはプロの矜持と自分の肉体だけを武器に前進を続けます。 従って、ハードボイルド小説における読者の楽しみは、物語を俯瞰し張り巡らされた伏線を辿りながら推理をすることより、むしろ作品世界に浸って、時に手に汗握り、時に痛みを感じながら事件の真相に迫ってゆくという部分にあると私は思います。 | |
| ハードボイルド小説の特徴と定義 | |
ハードボイルド小説の特徴としては、シャープな文体、感傷や既成の道徳観念を排した客観描写、そして粋な台詞や捻られたレトリックなどがあげられます。 | |
 では、ハードボイルド小説の定義は?と問われるとそう簡単にはいきません。ハードボイルドとは前述のような文体や形式だという意見もあれば、主人公の信条やキャラクターを指すのだという人もいます。誇り高い生き方や、己のルールを貫く頑な姿勢こそがハードボイルドの真髄だという考え方です。
では、ハードボイルド小説の定義は?と問われるとそう簡単にはいきません。ハードボイルドとは前述のような文体や形式だという意見もあれば、主人公の信条やキャラクターを指すのだという人もいます。誇り高い生き方や、己のルールを貫く頑な姿勢こそがハードボイルドの真髄だという考え方です。
要するに明確な一線があるわけではなく、一般に言われる「客観描写による非情で行動的な探偵を主人公とするミステリー」というような漠然とした表現にならざるを得ないのでしょう。 私個人としては、ハードボイルドに対するイメージは人それぞれ違って当然だと思いますし、厳密な定義を設けようとすることこそ、ハードボイルドらしからぬ無粋な行為だと思っています。 | |
| ハードボイルトド小説の歴史 | |
|
このサイトではハードボイルド小説を3つに時代に分け、それぞれ3人の作家を紹介しています。時代の分け方、作家のセレクトともに私の独断であることを予めお断りしておきます。 | |
 第一期「ハードボイルドの誕生」で取り上げたダシール・ハメットとレイモンド・チャンドラー、ロス・マクドナルドは御三家と呼ばれます。ハメットを始祖とするハードボイルドはチャンドラーとロス・マクドナルドによって完成され、黎明期というにはあまりに完成度の高い作品が生み出されました。「本格ハードボイルドはこの3人に始まり、この3人で終った」とも言われます。
第一期「ハードボイルドの誕生」で取り上げたダシール・ハメットとレイモンド・チャンドラー、ロス・マクドナルドは御三家と呼ばれます。ハメットを始祖とするハードボイルドはチャンドラーとロス・マクドナルドによって完成され、黎明期というにはあまりに完成度の高い作品が生み出されました。「本格ハードボイルドはこの3人に始まり、この3人で終った」とも言われます。
これ以降の作家は大きく「ネオ・ハードボイルド」と括られるのが一般的です。探偵のライフスタイルや人間個性が積極的に描かれるようになったのが特徴で、ハメットら御三家によって完成されたフォーマットに新たな要素を加えてみたり、あえて壊してみせたりと、様々な可能性が試された時期でもありました。 (※ネオ・ハードボイルド」は小鷹信光氏による造語ですが、そのまま使わせてもらいました) このサイトでは第三期として「進化するハードボイルド」すなわち現代という区切りを設けました。初期のネオ・ハードボイルドはベトナム戦争や冷戦構造というアメリカの閉塞した時代性と無縁にはいられませんでしたが、既にそれらの影響を受けない次の世代に移っていると思うからです。携帯電話やインターネットの登場で探偵たちの捜査手法に革命的な変化がもたらされたというのも理由の一つです。 | |
| チャンドラーの功罪 | |
|
ダシール・ハメットを始祖とするハードボイルド小説は、レイモンド・チャンドラーと彼の探偵フィリップ・マーロウの出現によって一気に読者の裾野を広げました。チャンドラーはデビューから70年以上経った今も、この分野を代表する作家と呼ばれ、その作品は世界中で読まれ続けています。 | |
 しかし、大衆受けしたチャンドラーは皮肉にも「ハードボイルドの方向性を誤らせた」とも言われます。非情であるはずのハードボイルドに感傷を持ち込み、「ハードボイルド小説=一人称記述」を定着させたために主人公の心情吐露を容易にしたというのがその理由です。また、主人公のマーロウがあまりに二枚目の正義漢に過ぎ、物語が勧善懲悪のファンタジー的になってしまった事実も否めません。
しかし、大衆受けしたチャンドラーは皮肉にも「ハードボイルドの方向性を誤らせた」とも言われます。非情であるはずのハードボイルドに感傷を持ち込み、「ハードボイルド小説=一人称記述」を定着させたために主人公の心情吐露を容易にしたというのがその理由です。また、主人公のマーロウがあまりに二枚目の正義漢に過ぎ、物語が勧善懲悪のファンタジー的になってしまった事実も否めません。
本来、ハードボイルド小説は客観描写に徹し、ことの善悪や人の心情に触れないものなのかも知れません。その意味で、ハメットの「マルタの鷹」や「ガラスの鍵」は、究極の完成形ともいえるでしょう。 (※2作ともハードボイルド史上に輝く名作です。是非挑戦してみてください) しかし、それを厳密に守ろうとすれば読者は限定され、また、ハメットのような高度な叙述法は後進の作家には大きな枷になっていたに違いありません。ハードボイルド小説を市井の娯楽として広め、多くのフォロワーを作り育てたという点で、チャンドラーは評価されてよいのではないかと思います。 | |
| チャンドラー作品、長篇と短篇の特殊な関係 | |
|
これからチャンドラーを読もうと思っているのであれば、まずは長篇から読むことをお勧めします。 | |
 それは、チャンドラーが短篇のプロットを繋ぎあわせて長篇を書く「首狩り(cannibalized)※」と呼ばれる独特の創作手法をとっているためです。名作「さらば愛しき女よ=さよなら、愛しい人」や「長いお別れ=ロング・グッドバイ」も、先に元となった短篇を読んでいると、「ん?これはどこかで読んだぞ」という事になってしまうのです。 (※cannibalizedには人肉食や供食いの他に再利用の意味がある)
それは、チャンドラーが短篇のプロットを繋ぎあわせて長篇を書く「首狩り(cannibalized)※」と呼ばれる独特の創作手法をとっているためです。名作「さらば愛しき女よ=さよなら、愛しい人」や「長いお別れ=ロング・グッドバイ」も、先に元となった短篇を読んでいると、「ん?これはどこかで読んだぞ」という事になってしまうのです。 (※cannibalizedには人肉食や供食いの他に再利用の意味がある)
逆に後で短篇を読めば「これがあの名シーンの下敷きになったのか」「これがあのキャラクターの原型か」と感激すること請け合いです。 | |
| 最初に読むチャンドラー | |
|
下に長篇全7作を発表順にリストアップしました。タイトルの前の○△×は私が個人的に初読に適しているか否かを判断したものです。もちろん「大いなる眠り」から順に読んでいただくのが理想です。また「プレイバック」には「しっかりしていなければ生きてゆけない。優しくなれなかったら生きている資格がない」というフレーズが登場する作品で知名度も高く、ここから入る方も多いようです。しかし、その前作「長いお別れ=ロング・グッドバイ」の事後談としての要素も多いのであまりお勧めできません。 尚、この評価は作品そのものの出来不出来を表わすものでは無い事を書き添えておきます。 | |
 ○「大いなる眠り」
○「大いなる眠り」○「さらば愛しき女よ」「さよなら、愛しい人」 ○「高い窓」 △「湖中の女」 △「かわいい女」 ○「長いお別れ」「ロング・グッドバイ」 ×「プレイバック」
|