![]()
硯塚犀角 短編小説
母と娘の鎮魂歌
「パパ、ほんとに行くのね」
加奈はさっきから何度も同じことを聞いている。麻奈が笑いながらソファーで飛び跳ねる。小学校一年生ともなると、震動で家が揺れるような気がする。二人とも大きくなったものだ。
加奈と麻奈は双子の姉妹で、二人とも未熟児として生まれてきた。特に妹の麻奈は極度の未熟児で、脳に障害が出るだろうと医者から言われたが、どうにか無事に育ってくれた。
「冬休みは、みんなでディズニーランドに行こうね」
隆史が私の顔を覗き見るように言う。急に今度の冬のボーナスが気になった。
「えーと、ディズニーランドって、どのくらいお金がかかるのだろう」それにしても、「地方公務員のボーナスって、どうしてこんなに安いんだろう」って、私は隆史に聞こえないように呟いている。
「じゃー、パパが残業して稼ぐから、加奈も麻奈も、ちゃんと勉強するんだぞ」
合併が決まってからというもの、隆史は残業が多い。
「魚沼市と合併するんだってさ」
「隆史が吐き捨てるように言ったのは半年前のこと。隆史は堀之内町に生まれ、東京の大学へ進学したが、卒業すると役場の職員として、生まれ故郷に戻ってきたのだ。
「いっしょに堀之内町の自然を守ってほしい」
それがプロポーズの言葉だった。もともと都会育ちの私は、家族の反対を押し切るようにして隆史の元へ嫁いできた。ここは町民どおしの結束が堅い。それでもヨソモノの私をちゃんと受け入れてくれる。嫁いで来た時も子供を産んだ時も、近所の人々が暖かく迎えてくれる。最初は隆史が役場に勤務しているからだと思ったが、決してそうではなかった。根っからの親切なのだ。
土曜日だと言うのに隆史は役場へ出かけて行った。もちろんディズニーランドの費用を捻出するためではない。魚沼市との合併で、問題が山積みとなっているようだ。
夕方、私は娘たちを連れて買い物に出かけた。スーパーのある魚沼市へ行くには山を三つ程越えなくてはならない。ワンボックスのワゴン車が、曲りくねった山道を軽快に走る。通い慣れた道だ。助手席のチャイルドシートには麻奈が座り、後部座席には姉の加奈がいる。
スーパーに着くと、さっそく隆史の好きな親子丼の材料を買い求めた。麻奈がチョコレートを強請ると、たしなめるように加奈が言う。
「麻奈ちゃんは、体が小さいんだから一個だけだよ」
加奈は自分よりも体の小さな麻奈をいつも何かと気遣っている。とても仲の良い姉妹だ。麻奈が答える。
「食べれなかったら、加奈ちゃんと半分こするもん」
私は帰り道を急いだ。隆史が帰るまでに夕飯の支度を済ませたかった。今夜は隆史の好きなサーモンのマリネも酒の肴に作るつもりでいた。
「加奈ちゃん、しっかり掴まっていてね」
トンネルを抜けると、紅葉が夕日に輝いて一層と鮮やかに映える。山深い中越の秋は神聖にさえ思える。豊かな自然が、私たちを優しく包んで守ってくれている。
私がアクセルを踏み込むと、急にセンターラインが蛇行した。ハンドル操作が全く効かない。慌ててブレーキを踏んだ。突然目の前に大きな岩が落ちてきた。私が目一杯ハンドルを回すと、車はガードレースに激突した。
遠くから子供の泣き声が聞こえてくる。加奈の声だ。
「ママー、助けて。怖い。手が痛いの」
目を開けると、ワゴン車は横転し土の中に埋まっている。土砂の隙間からこぼれる僅かな光で車内の様子が何とか見える。ハンドルの下半分が私の左胸奥深くに食い込んでいた。不思議と痛みは無いが、体は全く動かない。
助手席を見るとシートに血がべっとりと付き、麻奈の姿がない。私は焦った。必死で声を出そうとするが、声が出てこない。とにかく叫ぶ。
「麻奈ちゃん、麻奈。どこにいるの?」
すると耳元で麻奈の声がする。
「ママ、麻奈は大丈夫よ」
麻奈を抱きしめてやりたいが、麻奈の姿が見えない。
「だけど加奈ちゃんが怪我をしているの」
麻奈が言うと、さっきの泣き声が再び聞こえて来る。
「ママ、手が痛い。ママ、どこ?」
暗くて後部座席が全く見えない。それでも目を凝らしていると、少しづつだが見えてくる。後部座席の加奈は両腕が折れ、体の向きすら変えることができない。
「加奈ちゃん、ママはここよ。加奈はお姉ちゃんなんだから泣かないで。直ぐにパパが助けに来てくれるから」
私が励ますと、加奈は泣き止んだ。
「加奈ね、お腹が空いちゃったの」
すると後ろの方で、紙袋を開けるガサガサという音がする。麻奈が何やら捜していた。
「加奈ちゃん、これ食べて」
それはさっきスーパーで買ったチョコレートだった。麻奈がチョコレートの包みを開けると加奈が言った。
「麻奈ちゃんも食べて。半分こしようよ」
「ううん。麻奈はね、お腹が空いていないの。だから加奈ちゃんが全部食べて」
暗闇の中、麻奈は自分の手を使い、加奈の口までチョコレートを運んで食べさせている。食べ終わると、加奈は眠った。私が心配で眠れないでいると、時々、麻奈が話かけてきた。
「ママ、ディズニーランドに行こうね。絶対だよ」
ワゴン車を覆う土砂の隙間から、僅かな光が入り込んできた。どうやら朝の光ようだ。
「加奈、加奈」
呼びかけても返事がない。身動きのできない加奈は、ぐったりとしている。かなり衰弱が進んでいる。このままでは死んでしまう。
上空の方から轟音が聞こえてくる。ヘリコプターだ。
「助けて、助けて」
私は懸命に叫んだ。だが声にならない。ヘリコプターは山の辺りを旋回すると、どこかへ行ってしまった。加奈を見ると、顔が真っ白だった。加奈の血の気が無くなっていく。
「どうしよう」と焦っていると、麻奈が言う。
「ママ、パパを呼ぼうよ」
でも一体どうやって。「そうだ。携帯電話がある」と、私は叫んでいた。確か買い物袋の中に。暗がりの中で携帯電話を捜す。隆史に電話をしなくては。私は叫んだ。
「あなた、助けて。加奈が怪我をしているの」
「佳子か、今何処にいるんだ」
「山並トンネルを抜けた所にガードレールがあるでしょう。そこよ」
上空にヘリコプターが飛んでいる。轟音がけたたましく響く。ヘリコプターの中には隆史がいる。だが悪天候で、ヘリは私たちを発見できないでいる。麻奈が窓ガラスを開けて外へ飛び出していく。
「ママ、パパの所へ行って来る」
麻奈は外に出ると、ヘリコプターに向かい手を振った。
「パパ、ここだよ。早く加奈ちゃんを助けて」
ヘリがトンネルに差し掛かかる。トンネルは完全に崩壊していた。トンネルを出た所のガードレールも土砂で埋まっている。車らしき物は何処にも見当たらない。雨で視界が利かない中、隆史が目を凝らすとガードレールの脇で何かが一瞬だけ光った。
接近して見ると、それは車のバックミラーだった。ワゴン車が土砂で埋まり、大きな岩が運転席を完全に押し潰していた。とても生存者がいるようには見えない。私に隆史の声が聞こえてくる。
「お願いです。妻はまだ生きているんです。救助を急いでください」
夕方になって救助活動が始まった。すぐに近くに隆史が来ている。早くしないと加奈が危ない。だが、悪天候と余震で救助が難航している。夕刻になって、救助隊は去ってしまった。私は夜通しで加奈の名前を呼び続けた。
「加奈ちゃん、死んではだめ」
再び朝が来た。自衛隊員たちは、埋まった運転席を集中的に掘り起こしている。私なら最後で良いのに。私は一人の隊員に向かって、子供の囁く様な声で話した。
「後部座席よ、早く助けて」
その隊員が後部座席を見ると、土砂の中、岩と岩の隙間で土に塗れた何かが動いている。それは小さな手だった。隊員は興奮して叫んだ。
「生存者だ。生存者がいるぞ」
中越の大地震から四日後、新聞は加奈の救助を奇跡として報道した。母親と妹の救助にも期待が膨らんだ。しかし夕方になって二人の死亡が確認された。車がガードレールに衝突した直後、運転席と助手席は土砂崩れの岩に押し潰されて、二人とも即死だった。
注釈をつけます
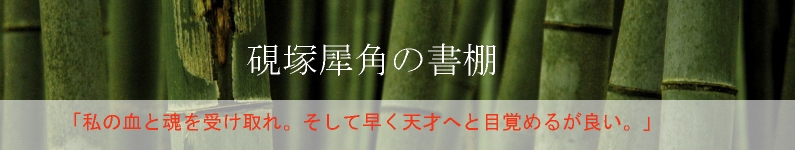







 前のページへ
前のページへ